「第二種電気工事士の資格を仕事に活かしたいけど、筆記試験って難しそう…」
「仕事が忙しい中で、効率的に勉強してサクッと合格する方法はないだろうか?」
そんな悩みを抱えていませんか?
こんにちは。二級建築士で、このブログ『n-1 Lab.』を運営しているPRAXISです。
私自身、長らく電気工事士の資格を取りたいと思いながらも、「電気理論は学生の頃に勉強した以来で、覚えてないしな~」と言い訳をしつつ、先延ばしにしていました。
しかし、DIYの幅を広げるためには電気工事士の資格は是非とも必要だということで、一念発起した結果、1週間の独学期間で、この第二種電気工事士の筆記試験(CBT方式)に一発で合格できました。
この経験から、私が実践した方法と、どのようにして合格までの道のりを歩んだのかを詳しくお伝えします。
この記事では、単なる試験対策だけでなく、「なぜ、DIYのためにこの資格を取るのか?」という本質から逆算し、私が実践した超効率的な学習の全記録と、その思考プロセスを余すところなく公開します。
この記事を最後まで読めば、あなたも最短ルートで合格するための、具体的な行動計画が手に入るはずです。
この記事で分かること
- まず知るべき「敵」の姿:筆記試験の全体像
– 試験概要と出題科目、合格基準と合格率、受験方式 - CBT方式と筆記方式、どちらを選ぶべきか?
- 目的を明確にする。
– なぜ、DIYに第二種電気工事士の資格が役立つのか? - 実録:私が筆記試験を1週間で突破した全スケジュール
- 合格の本質を突く、超効率的な3ステップ勉強法
- 本当に必要な参考書と、役立つ学習サイト
まず知るべき「敵」の姿:筆記試験の全体像 – 試験概要と出題科目、合格基準と合格率、受験方式
まずは、試験概要と出題科目、合格基準と合格率、受験方式を整理し、筆記試験の全体像を把握します。
試験概要と主題科目
第二種電気工事士試験には、学科試験と技能試験がありますが、技能試験は学科試験合格者のみが対象で、学科試験合格後に受験できます。前回の学科試験に合格している場合や特定の要件(下記注釈を参照)を満たしている場合は、学科試験免除者となります。
※一般財団法人 電気技術者試験センター > 第二種電気工事士試験概要
第二種電気工事士試験は年2回実施され、試験の実施時期は、例年、以下の通りです。
・上期試験
(学科試験:CBT方式4月下旬~5月中旬、筆記方式5月下旬/技能試験:7月下旬)
・下期試験
(学科試験:CBT方式9月下旬~10月中旬、筆記方式10月下旬/技能試験:12月下旬)
受験手数料はインターネットによる申込の場合9,300円、書面(受験申込書)での申込の場合9,600円です。個人的にはインターネット申し込みの方がお得なのでお勧めです。
学科試験は、50問出題され、全て四肢択です。これを2時間以内に回答することになりますが、時間に関しては比較的余裕があると思います。筆者も1時間くらいで解き終わることができました。また、技能試験は配られた配線図を見ながら、持参した工具で圧着、配線、接続、機器取付を行います。
出題科目は以下の通りです。
- 電気に関する基礎理論
- 配電理論及び配線設計
- 電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具
- 電気工事の施工方法
- 一般用電気工作物等の検査方法
- 配線図
- 一般用電気工作物等の保安に関する法令
この中で鬼門とされる科目は、1.電気に関する基礎理論ですが、これは例年5問~6問程度しか出題されません。仮にこれらを全て不正解となっても、残りの約45問(9割程度)で後述する合格基準を満たせば、試験を突破できますので、計算が苦手な方もご安心ください。
合格基準と合格率
合格基準は6割で、50問中30問正答するれば、合格できます。
第二種電気工事士の試験には、学科試験と技能試験がありますが、第二種電気工事士の学科試験の合格率は50~60%台、技能試験は70%台です。第二種電気工事士の試験は基本的な知識を問われるため、比較的合格率が高いことが特徴です。
特に筆記試験は暗記だけでも6割以上を目指せるために、先述した通り、計算問題が苦手で多少のミスをしたとしても、過去問学習と暗記を徹底していれば容易に合格できます。
※以下に第二種電気工事士試験の受験者情報統計を記載しているリンクを貼っておきます。
一般財団法人 電気技術者試験センター > 第二種電気工事士試験の試験結果と推移

合格率が高いということは、それだけ多くの人が挑戦している証拠ですね。
実際、年12万~13万人もの人がこの資格を受験しています。

わしもLogicoに教わりながら効率的に学習を進めることで短期間での合格を実現したで。
受験形式(CBT方式とマーク方式)
筆記試験の受験方式には以下の2種類があり、受験者は両者どちらかの方式を選択して受験します。
※技能試験は実地試験のみです。
筆記方式
従来の方式で、問題用紙とマークシートを用いて行う試験方式
CBT方式
問題用紙やマークシートの代わりに指定会場に準備されたパソコンの画面上で行う試験方式(受験申込完了後、受験日時及び会場を選択する必要があります。)
試験の解答方式が「紙に鉛筆でマーキングする」か「PC画面にマウス(キーボード)で入力するか」の違いであり、問題自体に両者の違いはありません。
従って、受験者にはどちらの受験方式を選択すべきかという問題が発生しますが、次にこの点について考察していきます。
CBT方式と筆記方式、どちらを選ぶべきか?
CBT方式と筆記方式のどちらを選ぶべきかという問題に答えを出すために、まずは両者のメリット・デメリットを整理してみます。
CBT方式のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 試験日程や会場を自由に選べる: 約3週間の期間内で都合の良い日時や受験会場を選べ、日程変更も可能です。そのため、仕事の都合をつけやすいです。 | 試験結果の控えを持ち帰れない: 回答した内容の控えを会場に持ち帰ることができないため、答え合わせができないです。 |
| 結果が早くわかる: 試験終了直後に合否がわかり、結果についてヤキモキせずに済みます。 | パソコン操作に慣れていないと戸惑う可能性: 普段パソコンを使わない人は、操作に慣れるまで時間がかかる場合があります。 |
| 図や配線図が見やすい: 図面を拡大できるため、細部まで確認しやすいです。 | — |
| 環境が整っている: 少人数で集中できる環境で、リラックスして受験できる場合があります。多くのCBT試験会場では耳栓を貰えるため、周囲の音に敏感な場合でも対応できます。 | — |
| マーキングの時間を短縮できる: CBT方式では解答の選択や変更をワンクリックで行うことができるので、解答にかける時間の短縮が可能です。 | — |
筆記方式のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 手書きでの回答に慣れている人や、パソコン操作が苦手な人に向いている: マークシート方式での受験経験がある人は多いと思いますので、慣れたやり方で回答できます。 | 試験日が固定: 指定された1日でしか受験できず、仕事や自身の予定と重なる可能性があります。 |
| 解答の控えを持ち帰れる: 後で自己採点をする際などに、解答の控えを持ち帰ることがでます。 | 図や配線図が見にくい: 問題用紙の図面を拡大できないため、細部が見にくい場合があります。 |
| ー | マーキングの時間がかかる: CBT方式に比べると、マーキング作業を50問分実行する分、時間が余計にかかります。 |
| ー | 受験環境は運任せ: 受験会場の環境は運任せであり、椅子や机が自分に合られる可能性があります。 |
結論:CBT方式で受験するのが得策
以上から、結論として、CBT方式を採用するのが多くの人にとって良いと判断します。
理由は以下の通りです。
- 日時や場所を自由に選べる:
CBT方式は、試験の日程が柔軟であるため、自分のライフスタイルに合ったタイミングで受験できます。これは、仕事で忙しい方々にとって大きな利点です。また、受験会場を自宅や仕事場の周辺に指定できることがあるため、移動コストが減ります。 - 受験環境をコントロールできる:
筆記試験はCBT方式に比べて、受験会場に不確定リスクがあり、適応力が求められます。一方、CBT方式は、あらかじめインターネットなどを使用して環境に慣れることができます。私もCBT方式に慣れるまでは不安でしたが、事前に模擬試験を受けることで自信を持って臨むことができました。 - 図が見やすく、回答スピードが上がる:
配線図を拡大することができるため、目が悪い場合でも対応しやすいです。また、マーク式による回答作業の時間を省くことができ、回答と回答の間のタイムラグがなくなることにより、考える作業に集中できます。 - 技能試験までの期間を多く取れる:
CBT方式を早めに受験することにより、技能試験までの勉強期間を長くとることができます。これにより余裕をもって試験に臨むことが可能です。

パソコンによる作業が苦手でない場合は、CBT方式の採用がおすすめです。
目的を明確にする。 -なぜ、DIYに第二種電気工事士の資格が役立つのか?
人それぞれの目的があると思いますが、私の場合は自分でできるDIYの幅を広げることです。
そのため、そもそも、「なぜ、リフォームの幅を広げるために、この資格が必要なのか?」という目的を明確にすることが、学習のモチベーションを維持する上で最も重要でした。
この資格を持つことのメリットは、法律的な縛りを気にすることなく、自分の手で様々な工事を行える点です。特に、家を自分の好きなように改造したいDIY愛好者にとっては、非常に大きな魅力です。各種工事が自分でできるようになることで、結果的にコストの削減にもつながります。
有資格者になると、以下のような工事が自分ででき、DIYでできることの幅が劇的に広がります。
- コンセントの増設・移設:
「ここにコンセントがあれば…」という願いを自分で叶えられます。壁紙を張替えるDIYをやろうと考えた際に、ついでにコンセントを増やしてやろうということができてしまいます。 - スイッチの交換・増設:
古いスイッチを交換したり、部屋の入口と出口にスイッチを増設(3路スイッチ)できます。スイッチカバーを交換することは、無資格者でも可能ですが、スイッチ本体の接続作業は電気工事士の資格がないとできません。
私の場合、骨董市で購入したレトロなスイッチに交換したいという目的を達成するために必要です。 - 直付けを引掛けシーリングに変更:
古い住居では直接照明器具が配線されていることが多いですが、これを便利な引掛けシーリングに変更できます。この工事を都度、職人さんにお願いしていると支出増えてしまいます。これくらいは自分で施工して、節約したいという願いを実現できます。 - 住宅設備機器の配線工事:
例えば、洗面化粧台などの住宅設備を自分で取付ようと思った時の配線や接続作業が、自分でできます。自分で水回り設備を据え付けたが、配線や接続は外注しないといけないという状況が避けられます。 - 碍子配線工事:
古民家などで見受けられる碍子配線も、電気工事士の資格があれば、実施できます。夢の古民家リフォームを自分の手で実現できます。 - 屋外の防水コンセント設置:
庭でのDIYや高圧洗浄機の利用が格段に便利になります。私の場合、屋外のコンセントが一か所(給湯器の近く)にしかなく、非常に不便に感じているので、これは是非ともやりたい工事です。
資格取得は、安全と知識を手に入れ、合法的にDIYの可能性を解放するための「最高の自己投資」なのです。

また、これらの作業は、無資格で行うと法律違反になるだけでなく、
火災や感電といった重大な事故に繋がる危険性があります。
【実録】筆記試験を1週間で突破した学習スケジュール
ここからは、私が実際にCBT方式の筆記試験に合格するまでの、リアルな1週間の流れを公開します。
使用したテキスト
テキスト:
『ぜんぶ絵で見て覚える 第2種電気工事士 学科試験 すい~っと合格 2025年版』
※私は2022年版の古本を400円で購入しました。
学習者が継続して勉強しやすいように、項目が並び替えられており、継続しやすい構成になっていることが特徴です。最初に取り掛かると躓きがちな電気理論が最後の章に配置されており、逆に比較的簡単な図記号や器具に関する知識が最初の章に配置されています。このように、初学者にとって、なにから取り組むと学習を継続しやすいかに配慮された書籍となっています。
その他、「はじめの一歩」という序章において、基本的な前提知識が解説されており、初学者が学習し始めるための導線が用意されているのも親切です。また、暗記項目をまとめた丸暗記ノートが付録でついており、これも便利です。
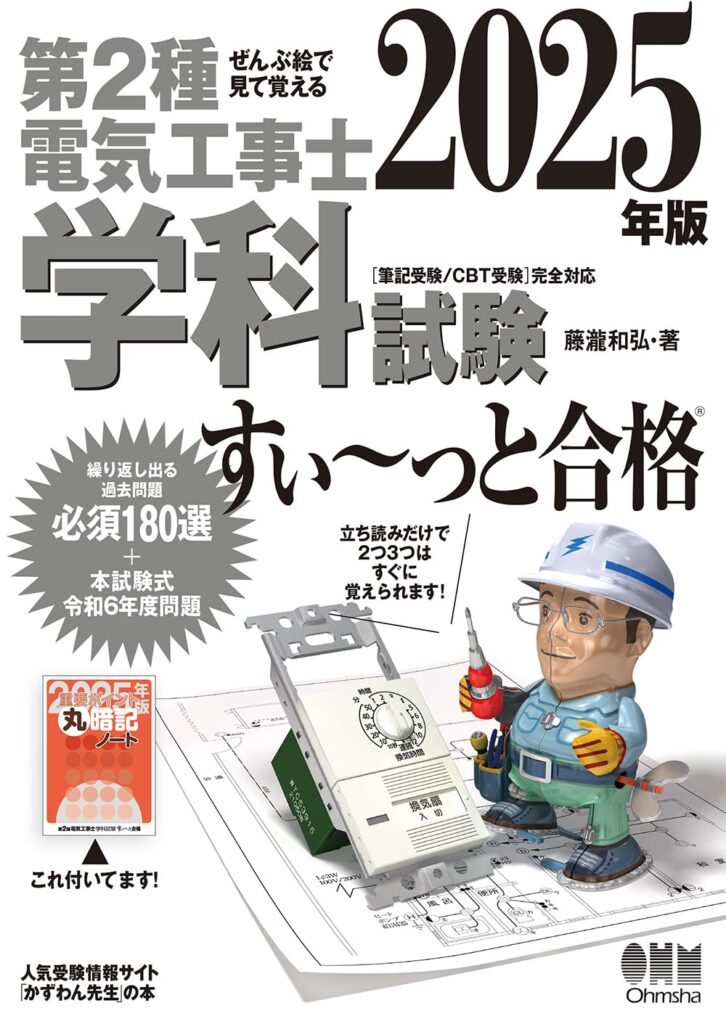
どの書籍を選ぶにしろ、一つの書籍を購入したら、浮気はせずに、そのテキストのみに集中するのがよいと思います。なぜならば、テキスト購入の選択に時間を費やしている間に勉強をした方が明らかに効率的だからです。
学習時間と合格までのタイムライン
総学習時間
平日は2〜3時間、休日は5〜7時間程度で、合計約22時間。
テキスト理解に12時間、過去問演習に10時間程度をかけました。
私はCBT方式を採用したので、自分で日程を入力しましたが、この日程は1週間で学習する期間を考慮して決めました。私はお尻に火がつかないとやる気が起きないタイプで、このように締め切りを決めることで、ダラダラと勉強せずに済みました。
タイムライン
- 1日目:
CBT試験の予約。一番早い日程で申し込み、自分を追い込む。中古で参考書を購入し、まずは過去問やテキストをパラパラと眺めて、全体構成を把握します。
この最初段階が非常に重要です。いきなり、頭からテキストを読み始めないことがポイントです。 - 2~3日目:
後述する「効率的な勉強法」で、テキストと過去問を並行して進める。ここに時間をかけ過ぎないことがポイントです。
また、一つの章(例えば、図記号)を読み終えたら、すぐに関連する過去問を解きましょう。抽象的な理解を具体的な理解に変換しながら、知識の定着を試みます。
ここまでが、全体把握と学習計画の策定、テキスト学習の期間です。以降、過去問中心の学習に移行します。
- 4~6日目:
過去問で7~8割以上取れる状態に。苦手な問題を重点的に復習。
過去問を2~3年分解くと、同じような傾向の問題が出題されていることに気が付きます。テキストで復習する際にどこに着目すれば良いのかが理解できるようになっていきます。
また、最初は良い点を取ることを目的とせずに、間違えた箇所を復習し確実に得点できるようにすることです。そうすると、同じパターンの問題が出題されるため、徐々に正答率が上がり、気づけば7割~8割以上の点が取れるようになってきます。 - 7日目(前日):
新しいことはせず、暗記事項(図記号など)の最終確認に徹します。
ポイントはここまでの演習で、過去問の6~7割以上得点できていれば、迷わず受験することです。完璧を目指さないことが重要です。なぜならば、6割以上回答できれば、満点であっても、60点ギリギリでも「筆記試験を合格する」という結果は同じだからです。
細かい知識にこだわらずに、必須暗記項目の確認と回答できなかった過去問の復習のみで大丈夫です。
そして、早く寝て受験日当日の体調を整えます。一夜漬けは避けましょう。寝不足で体調が悪いと凡ミスをしがちです。 - 当日:受験、そして合格。

受験当日は、緊張しつつも準備を整え、無事に試験を受けることができたで。これは、事前の準備や過去問演習が効果を発揮したからだと実感してるで。
合格の証明
以下が、実際にCBT試験会場で受け取った結果レポートです。60点以上で合格のところ、無事に9割の得点で合格ラインをクリアできました。
試験の際に渡される白紙メモ用紙が不足するのではないかと少し心配していましたが、結論から言うとこれは杞憂でした。メモ用紙が足りなくても、受付の人を呼べば、追加で渡してくれます。
また、CBT試験の場合は結果がすぐに分かりますので、試験結果を気にして、不安に思う期間を過ごす必要もありません。

合格の本質を突く!超効率的な3ステップ勉強法
私が実践した勉強法の本質は、「完璧を目指さず、合格に必要な知識を最短で脳に定着させる」ことです。具体的には、以下の3ステップで進めました。
ステップ1:敵を知る(テキストや過去問を眺め、全体像を掴む)
テキストを1ページ目から読み始めるのは非効率です。まずは過去問を1年分、答えを見ながらで良いのでざっと眺めます。「何が」「どのように」問われるのか、ゴール地点を先に確認することで、テキストのどこを重点的に読めばいいのかが自然と分かります。
例えば、過去問の構成は①一問一答形式で30問、➁配線図からの出題が20問ですが、
①の内訳は・・・
理論や設計の計算問題(10問くらい)⇒材料や工具の問題(8問くらい)
⇒施工の問題(5問くらい)⇒検査の問題(4問くらい)⇒法律の問題(3問くらい)
➁の内訳は・・・
出題順序はややバラバラな傾向にあるが、概ね図記号問題(10問くらい)⇒器具・工具・施工(7問くらい)⇒複線図の問題(4問くらい)
のように問題が出題されていると把握できます。
そうすると、自分は計算が苦手だが(最初の10問は後回しにするが)、残りの暗記系は確実に覚えて40問/50問の正答率を上げることを目標にしようという戦略が見えてきます。
または、逆に暗記系が苦手な場合で、特に数字を覚えるのが苦手だとすると、設計や施工の数字が問われる問題は後回しにして、計算だけで解ける問題と単純な暗記系(図記号や材料、工具など)を確実にして得点アップしようと考えることもできます。
このように自分なりの戦略を立てるための基本情報を得ることができるのです。
また、テキストの目次を確認したり、パラパラとめくることで、知識体系の全体像を把握します。そうすると、以下のようなことが何となく把握できます。
前提として電気理論・配電理論があり、そこから設計・施工・検査、法律に関する知識が展開します。また、電気工事の過程から考えますと、【設計】⇒【施工】⇒【検査】の各ステップで必要な前提知識として、部材(器具・材料・工具)と表現方法(図記号・複線図)があると理解できます。
このように、テキストの各章が解説している知識が、全体の中でどのような意味を持っているのかが把握できるということです。そうすると、先ほどのゴールの解析から導き出した戦略を実行するために、自分はどの章を先に勉強すべきなのか、念入りに復習すべきなのかという具体的なプランが見えてきます。より具体的な例はステップ2で解説します。

このように最初の段階で、「ゴール」と「必要な知識の全体像」を頭にインプットしておくと、テキストを読んだり、過去問を解いている時に、頭が混乱して迷子になることはありませんよ。
ステップ2:攻略ルートを決める(学習科目の順番)
ステップ1でゴールと全体像を把握し、戦略とプランが見えてきたら、次は具体的にどのようなスケジュールで試験を攻略するのか、検討していきます。多くの人は計算問題(理論)でつまずきがちです。そこで、私は以下の順番で学習を進めました。
- 暗記科目から攻める(図記号、材料・工具など):
勉強すればすぐに点数に結びつく、最も簡単な分野から始め、成功体験を積みます。この過程で助走することにより、残りの科目も一気呵成に取り組みやすくなります。それは、登山者が麓から登山を始めて、一歩一歩山頂を目指す過程と同じで、6合目7合目まで登攀すると、残りの山頂まではクライマーズハイにより乗り越えることができるのに似ています。
また、これらの科目は具体的な部品や工具が出てくるため、楽しく続けやすいということもメリットの一つです。私はホームセンターや秋葉原で実際の部材や工具を手に取ることで、具体的な実感をもって理解するようにしました。
全体の多くを占める比較的理解しやすい単純な暗記系を攻略すると、これらの知識を前提とした設計や施工、配線図や計算問題を解くための下地ができ、これらの理解が容易になるとともに、後半戦を一気に駆け上るための基礎体力ができます。 - 設計・施工・検査・法規を理解する:
暗記した知識が、どのように設計や施工で使われるのかを学びます。
規則や、数字、数式を暗記する必要がありますが、最初は完全に暗記する必要はありません。なぜ、そのような決まりがあるのかを理解することに注力します。
例えば、配線をどのうような間隔で支持しなければならないかなどの施工規則の問題があります。各配線方法や配管方法により施工する上での具体的な数値や規則が決められていますが、このようなルールの背景には「安全な施工」という一貫した思想が透けて見えます。この材料を安全に施工するならば、そのような基準になるなと実感をもって理解すると具体的な数字や規則がただの数字ではく、ある一定の規則をもった理由のあるものであることが分かり、覚えやすくなります。
これは、通常、実際の現場感覚により養われるものであるとは思いますが、想像力によりある程度の感覚を養うことは可能であると思います。 - 配線図や複線図を理解する:
より現場に近い知識を習得します。試験では、実際にどのように配線して接続するのかが問われます。具体的には、配線図や分電盤結線図が与えられるので、そこからボックス内でどのように接続するのかを考えて、必要なリングスリーブ(配線同士を接続するための部材)の個数を回答します。ステップ1で分析した通り、これらの問題は後半の20問で出題されます。
一見、難しいように感じるかもしれませんが、今までの知識をもとに、実際に工事をするなら、当然このような形で配線・接続で作業するだろうなという想像を紙に鉛筆で書き記すだけです。そして、そのように書き記した図面をもとに、問題を解答するだけに過ぎないと理解してしまえば、それほど怖くはなくなります。
※複線図は技能試験でも必要な知識です。必ずマスターしましょう。 - 最後に計算問題をやる(電気理論):
他の分野で7割方得点できる自信がついた状態で、最難関に挑みます。最悪、計算問題をいくつか捨てても合格できる、という精神的な余裕が、逆に理解を助けます。
また、計算問題が特に苦手な人は、最初の電気理論の計算問題を飛ばしてしまい、途中から解き始めることも戦略にすると良いかもしれません。計算問題以外を全て解き終わった後の余裕がある状態で、計算問題に取り組むことにより、最初から解き始めるようも冷静に対処でき、正答率が上がる可能性が高いです。
ステップ3:本質を理解し、完璧を目指さない
暗記は、「なぜその名前が採用されているのか?」「なぜそうなるのか?」という理由とセットで覚えると忘れにくくなります。
例えば、表示灯内蔵スイッチ図記号のL(ライト)やH(ホタル)など何の略字なのかを知っておけば、意味も分からず「L」や「H」という記号だけを暗記するよりもはるかに覚えやすいです。
また、照明器具は非接地側に取り付けてはいけないという施工方法に関する知識も、その理由(スイッチを切っていても電極に触れると感電してしまう。)を知っていれば容易に理解でき、そもそも暗記しなくてもよくなります。
このようにWhy(なぜそうなるのか?)を考えて本質を理解すると、それぞれの知識が断片的な暗記項目とはならずに、「電気工事のための理論」という体系を構成している不可分な要素として、有機的な知識に昇華されます。このような何故を問う理解は最初期には時間がかかりますが、最終的に人間の血肉となり、効率的に問題を解くだけでなく、実際の工事場面で役に立つ知識になります。そして、それこそが、工事作業を安全に確実に実行しようと計画している人間に最も役に立つものあることは言うまでもありません。
また、テキストを100%理解する必要はありません。過去問を解き、分からなかった部分をテキストで確認する、という「具体と抽象の往復」が最も効率的です。過去問で8割取れるようになれば、本番で合格できる実力は十分にあります。そこまで行けたら、すぐに受験して、次のステップである技能試験の準備にとりかかりましょう。

完璧を目指し過ぎて、受験を延期し過ぎると、結果として技能試験までの猶予が短くなり、ある程度不完全でも早い段階で筆記試験をパスした人よりも悪い結果を招く可能性があるからです。
おすすめの学習ツールと参考サイト
私が学習でお世話になった、質の高い参考書やWebサイトを紹介します。
- おすすめ参考書:
『ぜんぶ絵で見て覚える 第2種電気工事士 学科試験 すい~っと合格 2025年版』
図やイラストが豊富で、初学者でも直感的に理解しやすい一冊です。私が使ったのはこれだけです。 - 過去問演習サイト:
『HOZAN 第二種電工試験の虎』様
無料で質の高い過去問演習ができる神サイトです。移動時間などのスキマ学習に最適だと思います。
まとめ:筆記試験は、本質を掴めば怖くない
重要なのは、「完璧を目指さず、合格という目的から逆算して、戦略的に学習を進める」ことです。
多くの人にとって、免状を取得して、工事ができるようになることが最終目的だと思います。そのためには、試験を合格する必要がありますが、それは「過去問と同じような内容のテストを2時間以内に6割正答する」という行為で達成されます。そのように、割り切ってしまうことも時には重要です。
また、私の場合は、電気工事士の資格を「DIYで活用すること」が最大の目的です。
そのため、私には免状を取得することと、電気工事に関する知識を本質的に理解することが重要でしたが、常にそのことを意識しながら、学習を続けることで、脱線することなくゴールに向かって合格することができたと思います。
最後に、この記事があなたの資格取得の助けになることを願っています。
試験に挑戦することは決して簡単なことではありませんが、効率的な学習法を取り入れ、目的を明確にすることで、あなたも必ず合格することができます。
そして、第二種電気工事士の資格があなたのDIYライフを豊かにする手助けとなることを心から願っています。
次のステップへ
筆記試験の次は、いよいよ技能試験です!
工具の準備から、候補問題の攻略法までをまとめた技能試験対策の記事も、ぜひご覧ください。
【次の記事】第二種電気工事士・技能試験対策の記事へのリンク(準備中)
また、この資格を実際にDIYでどう活かしていくのか、
その全記録をまとめたハブ記事はこちらです。
これからのDIYライフを楽しむために、第二種電気工事士の資格を最大限に活用して、自宅を最適化していきましょう。技能試験や実際のDIYプロジェクトに向けての準備も怠らずに進めていきたいと思います。



コメント